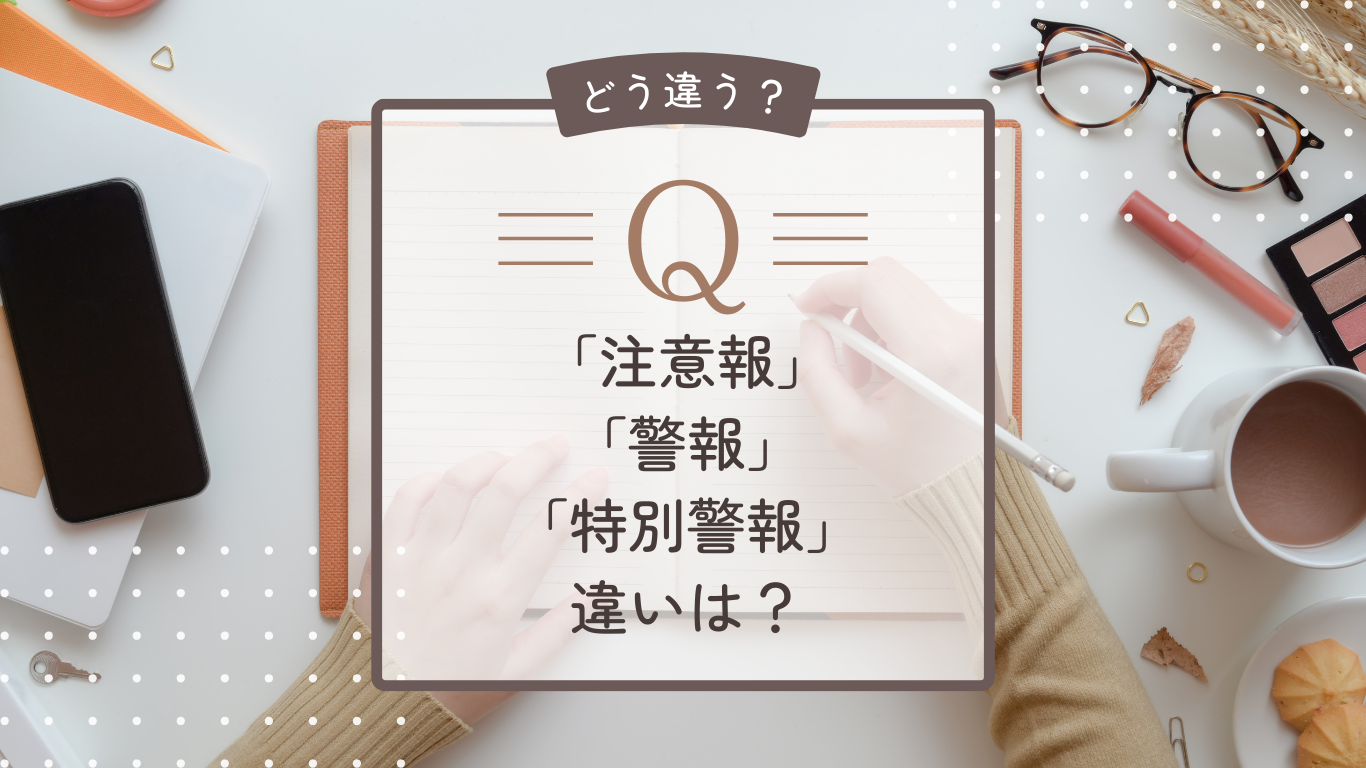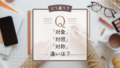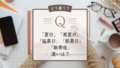自然災害の発生が懸念される際に、人々への注意喚起や警告として発表される情報には、「注意報」「警報」「特別警報」というものがあります。
それぞれの違いを見てみましょう。
「注意報」とは
「注意報」とは、災害が発生する可能性がある場合に、その危険性を知らせるために発表される予報です。
対象となる現象には、気象、地震津波、高潮、波浪、火山、洪水などがあり、さらに気象注意報の中には、雷や強風、大雨、大雪、高潮、暴風、融雪、なだれ、乾燥、霜、氷、着氷、雪氷、霧など、細かく分類された種類があります。
「警報」とは
「警報」は、より深刻な災害の発生が予想される場合に発表される予報です。
こちらも対象となる現象は気象、地震津波、高潮、波浪、洪水などで、「注意報」と同じですが、具体的な気象の種類には違いがあり、暴風、暴風雪、大雨、大雪といった4種類に絞られています。
「特別警報」とは
「特別警報」は、極めて異常な現象が予測され、そのために大規模な災害が発生する恐れが非常に高い場合に発表されるものです。この「特別警報」は、2013年8月30日から運用が開始された新しい警報で、対象となる現象には、気象、地面現象、海嘯、波浪があり、特に気象においては、暴風、暴風雪、大雪、大雨の4種類に区分されています。
これらの警報は、被害の可能性が高まる順に「注意報」→「警報」→「特別警報」となり、特別警報が発表された際には、数十年に一度あるかないかの大災害が予測されるため、最大限の警戒が必要です。避難指示や避難勧告に従い、早めの行動を心がけることが大切です。
なお、これらの警報や注意報に関する基準は、全国的に共通する部分もありますが、具体的な基準は地域ごとに異なります。これは、各地域の地形や地盤の強度、気候条件が異なるためです。例えば、降雪量が多い北海道や北陸地方と、降雪が少ない東京都とでは、同じ雪の量でも災害のリスクが異なり、そのため警報や注意報の基準も異なってきます。
最後に、「注意報」「警報」「特別警報」については、それぞれの主旨や定義に応じた使い分けがされています。警報や特別警報は「気象警報」としても定義されており、注意報は「気象警報実施行」に基づいています。
このように、それぞれの警報や注意報の役割を理解し、適切に対応することが重要です。